 |
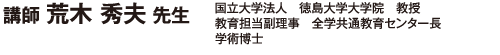

筑波大学大学院博士課程体育科学研究科体育科学専攻修了。運動学・運動生理学にもとづき、運動の発生・発達に即して身体、脳、心への刺激を与えて、心身の成長を促す「コオーディネーション運動」をアカデミックにわかりやすく指導。その内容はスポーツ分野にとどまらず、教育、社会学、食など幅広い分野に及ぶ。新しい人間科学的なコオーディネーショントレーニング理論の開拓者。2008年北京オリンピック陸上競技男子400mリレー銅メダリスト 朝原 宣治氏が主宰している陸上競技クラブ「NOBY T&F CLUB」の運動プログラムを監修。 |
|---|

生まれて歩き始めた時、歩くための塾に通った人はいません。ほとんどの運動は自らがそれなりのやり方で、自然に覚えていきます。蝶は成虫となって羽ばたく前にサナギの時期を経ますが、このサナギの時期に意味があるのです。この中身がコオーディネーションなのです。簡単に言えば「組み合わせる」ということです。
人間は一つひとつの器官の能力では他の動物たちにかないません。ですから、個々の能力を自由に組み合わせることで棲息域を広げてきました。人間本来のこの「組み合わせる」ことを忘れると、他の動物のように型にはまってしまいます。アンチ思考型の勉強、型優先の運動は副作用が起きるのです。サッカーや野球などの場合でも、ある一つの練習を徹底的にすると逆に下手になってしまう。型にはまり、特化型になると「なぜ?」ということを考えなくなり、環境に適応しにくくなるためです。
また、人間はこの世に生まれてから作り上げていく生き物です。何でも早くできたからといって優れているとは限りません。むしろ、優秀な能力を発揮する子どもは遅めの子どもが多く、早くからカチッと教えようとすると間違ってしまう。スポーツ、音楽、コミュニケーション、勉学など、人間の一つひとつの要素をうまく構成する、組み合わせのコツをつかむことによって、知性、感性を築き上げていく。それが本当の人間であると考えています。

生まれたばかりの赤ちゃんは1歳半あたりから、栄養と感覚運動刺激を求めて運動欲求が起こります。成長するにつれ欲求が一通り埋まると、次にスポーツをしたり楽器を奏でたりするプレイ(遊び)欲求が生まれます。プレイ欲求に共通するものは新しいものを「創る」ことですが、欲求が間違って埋まる場合があります。ある会場に入った子どもはあっちこっち走ります。体の筋肉が動き目の前の景色がどんどん変わるにつれ、視覚の変化も総合され知的な発想能力となります。ところが、3Dで空間認知をやったと思うと間違ってしまうのです。
また、子どもに必要な栄養源としてチョコレートやポテトチップスばかりを食べさせると味蕾細胞が崩れ、あたかも必要な栄養源をとったかのような錯覚を起こします。大脳味覚が変形して満たされたと勘違いし、依存症になることもあり十数年後に副作用が出ます。
運動でのリスクとしては、運動不足の他に運動のアンバランスがあります。普通の子どもは同じ運動にはすぐに飽きてしまい、つい「なんとうちの子は飽きっぽいんだろう」と思ってしまいがちですが、小さい頃には一通りの運動を経験した方がいいのです。子どもはいろんな能力を身に付けていくために飽きるのです。運動が偏ると特化型になり、「キレやすい落ち着かない」情緒不安定な人間になりかねません。昔はおとなしくてコミュニケーションをとれなかった人が事件を起こす確率が高かったのですが、今は普通の人が起こします。早期発見、早期治療が大切です。

子どもは特に平衡能力を身に付けること、バランスをとることが重要で、これが精神的な土台となります。鬱病の傾向があると平衡能力も落ちますが、「姿勢を直しなさい」と指導するのではなく、崩れた姿勢に違和感をもつ感受性を育むことが大切です。食欲に関しても同様で自然のものを食べるという本来の食欲を戻すこと、喉が乾いたら真水を飲みたくなる感覚をとり戻すことが大事なのです。
また、手が届くところにもっていって見せる、触わらせることも重要です。そして、手が届く範囲から目に見える範囲へ、見えなくても想像できるようにと伸ばしていきます。ここから空間や心理、数学の定理や自分の将来のビジョンなどの抽象的な思考、想像的知性につながっていきます。
球技を教える場合は、まずボールを手に持たせて馴染ませる。そして、投げる時は必ず目線の下に投げる。スポーツにおいても、こういう基本的なことが抽象的な思考につながっていきます。そして、また基本に戻る。この繰り返しによって上達していくのです。
調理や料理にも人間の本能に即した行動様式があります。野菜嫌いの子どもは、本来の野菜の食べ方と違う形で、大人の文化を子どもに同化させようとするところから生まれます。なぜ京料理やフランス料理はお皿に少量ずつ入っているのでしょうか。お皿の真ん中に少量の野菜をポンと置いておくと、野菜嫌いの子どもでも手を出したくなるでしょう。

認知階層としては言葉が上で運動感覚が下。やると言葉が出てきます。包丁の使い方を教える場合も、見て教えるより包丁を持って自分でやると「体全体を横にするのがいい」などの言葉が出てきます。これは感性がもっている知性です。試験のために覚えた知識は、本当の知性と言えるのでしょうか。動くことと考えることが一体になっていないのです。感性、知性は「身のこなし」の中で学ぶものであり、その学び方を子どもの時に経験してきたかどうかが大事です。
食べることも同じ。見た目、食感などによる総合的な風味は、言葉や体の動きで学習します。牡蠣の嫌いな人も「組成が人間の体の特性とよく合う」という話を聞くと、おいしく感じることがあります。聞いた言葉を体の感覚で身体化する。食べたい欲求から食べ物に対する「言語化」の形で発達するということです。
環境からの刺激は運動や何らかの感覚を求めます。自然の中で生まれた動きは適正な欲求を引き起こすのです。食については「食べてみたい」という適正な欲求を引き出すこと。子どもがもっている一つひとつの能力をどんどん組み合わせて、大人の発想をくみ上げていく。食の知識も運動によってつなぎ、身体化する。数学や音楽などの勉強においても何が決定的か。有名な数学者ポアンカレや文学者のバルザックも「身体である」と書いています。「動くこと」が原点です。知性、感性、身のこなしが満たされたスポーツ活動こそが、一人ひとりの考え方を育むのです。